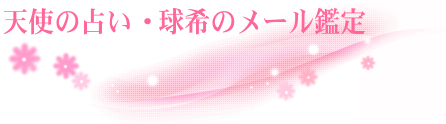|
素読のすすめと物語(1) |
幕末の学者志士で有名な吉田松陰は、幼くて家が貧しい頃、叔父について畑を耕しながら、儒学の素読をさせられたとあります。昔の寺子屋の授業も、読み書きと素読であったろうと思います。要は何度も何度も読んで丸暗記したということなのです。
ここでもキーワードは"反復"ということなのです。そして、"おもしろい"ということです。「反復する訓練の授業=おもしろい」という条件反射を作ってやることなのです。そうすると本当におもしろいことが起こるのです。ただ闇雲に覚えていた子供たちが、ある時ある日突然に、"ハッと"思い出すのです。ある条件と環境が出てくると、昔覚えていたことがなんだったのかがわかるのです。これを"悟り"というのです。こうなると楽しいですよね!
吉田松陰の松下村塾は、そういう素読だけに飽き足らない有能な士が集まり、自由に討論したというから、そこからくるエネルギーは大変なものだったのに違いありません。
物語にもそういう効能があるのです。ちょっと前には、テレビで大変人気があったのは「日本昔話」です。"ぼーや、よい子でねん寝しな"ではじめるテーマソングは、子供たちに評判がありました。(少なくとも、我が家の子供にはですが・・・)
結論は決まっているのです。貧しくても、ちゃんと正しいことをしている人が最後は幸せになるというものです。こういう童話を、寝物語で読んでもらった人は幸せですよね!
素読のすすめと物語(2)
水戸黄門のワンパターンドラマが受けるのも、こういう人間の持っている公式みたいな文化があるからなのです。
問題は、こういうVSOPのオールドリザーブを小さいときから、いかに自然な形でインプットさせることができるかなのです。そういう意味で、現代の子供のゲーム文化は、人間のもっとも大切な"戒め"という文化を破壊してしまう危険性があるのです。
江戸時代は、武家では儒学が(朱子学ー滅び行く宋の時代を救わんとした朱子による儒学)、町では寺子屋が、裕福な豪農の子弟は塾へ、商人たちはこぞって石田梅岩らの提唱した"心学"を学び、日本人は日本教ともいうべき戒め文化を発展させていったのです。
問題は、こういった反復訓練からくる教育的な効果が、戦後全くなくなってしまったということです。学校はいわゆる教科という実務だけを教えるようになってしまったのです。そして、家制度が崩壊して、戒め的な存在としての父親が不在になり、両親とも働かなければ食べていけないと、親不在の家庭が目白押しに増えている現状は、どんな教育論を並べても意味がありません。
さて、本題に入りましょう!反復という訓練は、創造能力の啓発につながるかということなのです。その答えは、反復という訓練は、創造能力が啓発されるということです。
自分の教訓は人生の蓄積である(1)
反復という訓練は創造能力の啓発になる。ということのポイントはどこにあるかというと、それは人間と動物の構造の違いをみればいいのである。
動物は、自然の摂理によって、時がくれば成獣になり、子孫を繁殖し、後孫にその種子を残していくのであるが、どうも人間だけは違うのである。確かに肉体だけは、時がくれば成人の体つきと機能を備えるようになるが、人間の心の成長は、動物のように自然の摂理任せとはいかないのである。
キーワードは自由意志による自己創造ということなのである。要するに自分の心は自分で育てるものなのですよ!ということなのである。従ってよく子供がいう「自分の力で大きくなった」というのも間違いではないのである。
では親は何をすればいいのであろうか?「飯を食わせればいい!」こんなのは肉体の親であって、心の親ではないのである。子供が欲するのは"心の親"なのである。子供の心の親になるとはどういうことなのであろうか?ちょっと考えてみよう!
「親」という漢字をみてみると、"木の上に立って見る"と書くのである。これが親なのである。動物のカバの親子を見てみるとおもしろいのである。カバはご存じのように首がなくてそのまま胴体のような動物ですから、当然首は曲がらない。(借金で曲がらない人間とは違う)
|